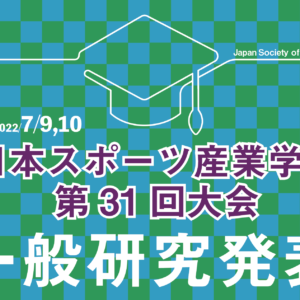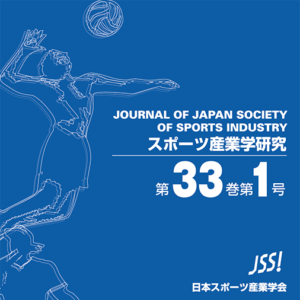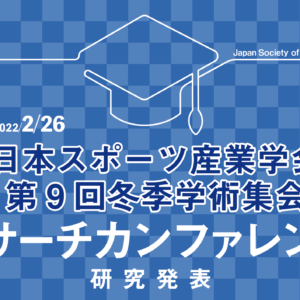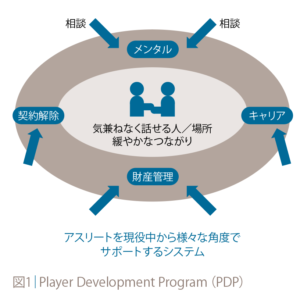スポーツ産業学研究第35巻第2号
【原著論文】
中学校運動部活動顧問のコーチングスタイルと地域移行ビジョン:北海道におけるソフトテニス部の調査から
小峯 秋二, 川西 正志, 竹田 唯史
JSTAGE
Jリーグのアウェイ観戦におけるプル要因:アウェイ観戦経験の有無に着目して
太田 明李, 伊藤 央二
JSTAGE
ソフトボール競技における看護の役割-参与観察からの検討-
式澤 明子, 澁木 琢磨, 児玉 ゆう子
JSTAGE
【研究ノート】
地域から支持されるJリーグ地域型クラブのホームタウン活動に関する事例研究
田中 奏一
JSTAGE
日中両国におけるスポーツ振興くじの売上に影響する要因-高齢化に着目して-
王 一楠, 間野 義之, 佐藤 晋太郎
JSTAGE
【レイサマリー】
中学校運動部活動顧問のコーチングスタイルと地域移行ビジョン:北海道におけるソフトテニス部の調査から
小峯秋二(北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科)
川西正志(北翔大学生涯スポーツ学部)
竹田唯史(北翔大学生涯スポーツ学部)
本研究の目的は,中学校ソフトテニス部の部活動指導における顧問のコーチングスタイル(以下,CS)と地域移行ビジョンとの関連について明らかにすることである.調査は,2022年8月から9月の1ヶ月間に,北海道の中学校ソフトテニス部指導者516名を対象にWebアンケート調査を実施した.CSの因子構造の分析には,最尤法プロマックス回転を行ない5因子が抽出された.各因子は,1)指導者倫理,2)多様性・尊厳,3)勝利・技術,4)平等,5)教育効果と命名した.次に,ウォード法による階層的クラスター分析を行ない4群に分類した.各因子の合計点を算出し分散分析を行ない,1)競技力の向上を重視した「競技スポーツ志向型」,2)人間形成や社会性の育成等を重視した「人間形成志向型」,3)生涯スポーツやQOLへの教育効果を重視した「生涯スポーツ志向型」,4)生徒の活動の支援を重視した「活動支援型」と命名した.CGと地域移行ビジョンについては,地域クラブ活動運営への参加意思にだけ有意差がみられ,競技スポーツ志向型(73.9%)が最も高く,人間形成志向型(41.1%)が最も低かった.
Jリーグのアウェイ観戦におけるプル要因:アウェイ観戦経験の有無に着目して
太田明李(中京大学大学院スポーツ科学研究科)
伊藤央二(中京大学スポーツ科学部)
近年,我が国においてはアウェイ観戦に伴う観光行動であるアウェイツーリズムが注目されている.特に,Jリーグにおいては,観戦前後にアウェイ地域の地域観光や地元の食事を楽しむサプリメンタル観光行動を促進することで,Jリーグ観戦の新たな魅力を創出している.しかしながら,多くの研究がホームチームのファンの観戦者行動に焦点を当てており,アウェイ観戦者行動については等閑視されている傾向にある.アウェイ観戦行動の理解を促進するためには,目的地特性に基づく動機であるプル要因を明らかにすることが重要であると考えられる.したがって本研究の目的は,アウェイ観戦におけるプル要因についてアウェイ観戦経験者と非経験者間で比較検証することとした.
本研究の目的を達成するため,グランパスファンを対象とする質問紙調査を実施し,280部の有効回答を得た.アウェイ観戦におけるプル要因として,「アウェイスタジアムへのアクセスのしやすさ」「自宅からアウェイスタジアムまでの距離」「アウェイスタジアムまでの交通費」「アウェイスタジアムの観戦環境」「アウェイ観戦に必要なチケット代」「アウェイ観戦をすることでもらえる特典」「アウェイスタジアムがもつ歴史」「アウェイスタジアムで行われるイベントの内容」「アウェイスタジアムの話題性」「アウェイスタジアム周辺地域の魅力」の10項目を,先行研究を基に選定した.分析としては,2023シーズンにおいて1試合以上のアウェイ観戦経験がある回答をアウェイ観戦経験者,1試合もアウェイ観戦経験がない回答をアウェイ観戦非経験者として分類した.そして,ホテリングのT2検定によって2つのグループ間のプル要因の平均値を比較した.その結果,アウェイ観戦経験者は,「アウェイスタジアムの話題性」と「アウェイスタジアム周辺地域の魅力」においてアウェイ観戦非経験者よりも有意に高い値を示した.一方,アウェイ観戦非経験者は,「アウェイ観戦をすることでもらえる特典」と「アウェイスタジアムで行われるイベントの内容」においてアウェイ観戦経験者よりも有意に高い値を示した.
本研究は,Jリーグのアウェイ観戦を促進するためには,観戦者のアウェイ観戦経験に応じたプロモーションの導入が効果的であることを示唆している.アウェイ観戦経験者においては,スタジアム独自の特性を強調することや,観光地との連携を深めて観戦前後のサプリメンタル観光行動を促進することで,継続的なアウェイ観戦行動を促すことが重要となる.一方,アウェイ観戦非経験者においては,アウェイ観戦者へのノベルティを組み込んだイベントを導入するなど,アウェイ観戦者にとってイベント性の高いサービスを提供することが,新たなアウェイ観戦者の獲得に向けた効果的なプロモーション戦略となると考えられる.
ソフトボール競技における看護の役割-参与観察からの検討-
式澤 明子(聖徳大学)
澁木琢磨(星槎大学大学院)
児玉ゆう子(兵庫大学大学院)
スポーツイベントでは、様々な医療職者が救護スタッフとして従事している。しかしながら、スポーツ現場における看護師の具体的役割や、必要とされる知識・技術に関する情報は整備されていない。さらに、競技会場へ看護師を常時配置するための教育体制や人材育成の仕組みも未だ確立されておらず、今後の課題とされている。
ソフトボールは老若男女問わず幅広い年齢層で親しまれている競技であるが、競技の特性上、歯牙・眼球・額などの顔面部や手指を中心とした上肢の外傷が多く、さらに心臓振盪といった生命の危機に直結するリスクも存在する。以上のことから、本研究ではソフトボール競技現場において看護師が救護活動を担ううえで必要とされる知識や技術を明らかにすることを目的に、参与観察を通じて看護師の役割について検討した。
特定のソフトボールチームを研究対象として、約1年間合計16回の参与観察を実施した。観察の結果、選手や観客、審判員に外傷・急病のリスクがあることが確認され、生命の危機に直結する事例も認められた。このことから、ソフトボール競技において看護師には、医学知識に基づく判断と応急処置に加え、対象理解に基づいた精神的ケアの提供を求められることが示唆された。
一方で、各チームに看護師を常駐させるには、財政的な制約があることも明らかとなった。今後は、多様な競技に対応できる看護師の育成を推進するとともに、スポーツ救護に従事する前に対象競技のルールや特性、外傷の傾向等を習得できる体制を構築することが急務である。看護師の活動領域の一つとして「スポーツ救護」を確立することは、安全な競技環境の整備に寄与するのみならず、スポーツ振興にも貢献し得ると考えられる。
地域から支持されるJリーグ地域型クラブのホームタウン活動に関する事例研究
田中奏一(京都先端科学大学)
本研究では、企業内のサッカー部としてではなく設立された地域型クラブであるJ2リーグ所属のファジアーノ岡山を事例に、限られた資源の中でも地域から高い支持を得ている理由をホームタウン活動の視点から探りました。ファジアーノ岡山は、クラブの創成期にはホームタウン活動での選手の露出や活動回数を意図的に抑え、活動の希少性を高めてブランド価値を構築しました。また、地域との不公平感を防ぐため、活動の選定には優先順位を設け、メディアを活用して広く認知を促進しました。さらにコロナ禍を機に、社会体育施設の指定管理や一般社団法人の設立を通じて活動拠点を拡大し、地域貢献の幅も広げています。クラブの理念に基づき、段階的に戦略を進化させてきたこれらの取り組みは、他の地域型クラブにとっても持続的な地域連携のモデルとなり得ることが示唆されます。今後は、J1リーグに昇格したファジアーノ岡山の変遷を追跡することで、地域型クラブがより長期的な計画を立てる上での有用な示唆を得られると考えています。
日中両国におけるスポーツ振興くじの売上に影響する要因 -高齢化に着目して-
王一楠(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科)
間野義之(びわこ成蹊スポーツ大学)
佐藤晋太郎(早稲田大学スポーツ科学学術院)
本研究は、高齢化が進む日本と中国を対象に、高齢化がスポーツ振興くじ(以下、スポ ーツくじ)の売上にどのような影響を与えたかを明らかにすることを目的とした。日本 ではすでに「超高齢社会」に突入しており、中国でも近年急速に高齢者の割合が増加し ていた。両国ともに、高齢者の健康維持や社会参加の支援が政策の重要な柱となってお り、スポーツはその手段の一つとして注目されていた。
一方、スポーツを支える財源には限りがあり、その中でもスポーツくじの収益は非常に 重要な役割を果たしていた。スポーツくじは、スポーツ施設の整備、競技力の向上、子 どもや高齢者の健康づくり支援など、さまざまな分野に活用されていた。しかし、近年 では新型コロナウイルスの影響や社会構造の変化により、売上が減少傾向にあり、持続 的な運営が課題となっていた。
本調査では 2013 年から 2021 年までの日本 47 都道府県および中国 30 地域のスポーツく じ売上データを収集し、さらに高齢化率、GDP、所得などのマクロ経済指標も取得した。 収集したデータはパネル形式で整理され、計量分析ソフト STATA を用いて、双方向固定 効果モデルなどの統計手法によって分析が行われた。また、ハウスマン検定や内生性検 定(2SLS 法)、サブグループ分析も実施され、分析の信頼性を高めた。
その結果、日本・中国ともに共通して、高齢化率が上昇するとスポーツくじの売上が有 意に減少する傾向が確認された。日本では高齢化率が 1%上昇することで売上が平均 0.038 単位、中国では 0.083 単位減少するという結果が得られた。特に中国の方が影響 が大きく、この違いには地域経済の格差や文化的背景が関係していると考えられた。
さらに、サブグループ分析では、経済発展レベルの低い地域ほど、高齢化率の上昇によ りスポーツくじの売上が大きく減少する傾向が強いことが明らかになった。これは、可 処分所得が限られている地域では、高齢者の余暇消費が抑えられる傾向があること、ま た収入が固定されている高齢者がリスクのある支出を避ける傾向にあることが影響して いた。
加えて、日本と中国ではスポーツくじに対する社会的イメージにも違いが見られた。日 本では、スポーツくじ(toto)の収益が地域スポーツの環境整備などに活用されること が広く知られており、「地域貢献」の一環として受け止められていた可能性が高い。一 方、中国ではスポーツくじの収益は教育や福祉など幅広い分野に使われ、「高額当選」 や「運試し」といった娯楽性が強調されていた。このような文化的違いも、高齢者の購 買行動に影響を与えていた可能性がある。
本研究から導かれた示唆としては、今後のスポーツくじ政策において、高齢者にも魅力 を感じてもらえる商品開発や、健康・地域貢献と結びつけた使途の明確化が重要である ことが挙げられる。例えば、収益が高齢者の健康促進や地域活動に還元されることを示 すことで、「自分の生活にも役立つ」という納得感を高め、購入意欲を高める効果が期 待される。
また、広告や広報においても、「スポーツくじを買うことが社会貢献につながる」「健 康や孤独対策にも効果がある」といったメッセージを発信することで、より多くの高齢 者の関心を引くことができると示唆された。
本研究は、スポーツ財源の安定確保と高齢化社会への対応という二つの課題を結びつけ た新たな視点を提供した。今後は、より長期的なデータの活用や、質的調査(インタビ ューやアンケート)を通じて、高齢者の行動心理や購買動機を深く理解する研究の展開 が期待される。また、他国との比較研究や、公営競技を含む幅広い調査への発展も有意 義であると考えられる。