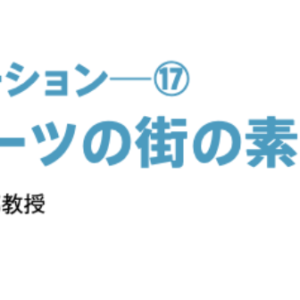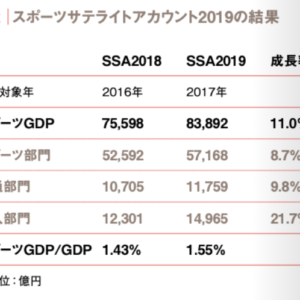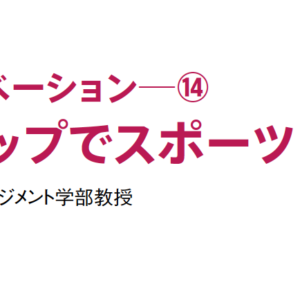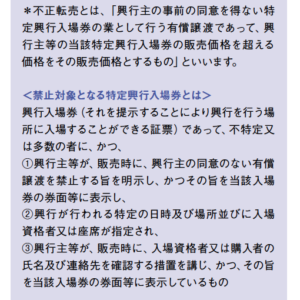日本代表の法務 ~日本代表の移動、滞在をめぐる問題
New trends in sports law
日本代表の法務
〜日本代表の移動、滞在をめぐる問題
松本泰介 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 博士(スポーツ科学)/弁護士
パリオリンピックパラリンピックが終了しました。東京大会は無観客でしたので、観客が入った会場で行われたオリンピックパラリンピックは久々でした。パリという街並みと一体化したオリンピックパラリンピックでしたので、大きな熱気を感じる大会となりました。
活躍した日本代表選手は、表彰台や当日のテレビ出演など露出が多くなりますが、その後日本に帰国し、空港税関通過後の到着ロビーなどもよく報道されています。閉会式を待たずに帰国する選手も多いので、意外と早く帰国するとお感じの方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、日本代表の移動、滞在をめぐる問題に関して、解説してみたいと思います。
1.莫大な費用、膨大な事務負担
日本代表が海外遠征する場合、当たり前ですが、一般の飛行機や宿泊施設を利用しています。日本代表や中央競技団体といっても、特別な移動手段や宿泊施設が常に用意されているわけではありません。あくまで1つの民間組織ですので、基本的に中央競技団体が自ら手配することになります。旅行代理店や航空会社などの法人窓口を利用して、人数分を予約し、移動、宿泊しています。スポンサー先からの提供などもあるのではないか、と思われることもあるかもしれませんが、航空会社や宿泊施設の場合、搭乗する費用も非常に大きなものになりますので、一定の割引はあったとしても、代金を支払う場合がほとんどです。
日本代表の海外遠征において、交通費や宿泊費は大きな金額になります。1つの大会でどのような移動をしているかがフォーカスされがちですが、昨今は海外と試合を行わないと日本代表の強化につながらないため、1年間に何度も海外遠征している場合もあります。それだけでも2倍3倍の費用が必要になってきます。また、日本代表と言っても、男女、年代別など様々な日本代表が活動しており、それぞれがスタッフを抱えながら、世界中で遠征をおこなっているため、その費用を負担する中央競技団体の支出としては非常に大きなものとなります。中には、中央競技団体の予算減の関係で、年代別の日本代表は海外遠征に行けないなどの影響が出ている団体もあります。よく強化にお金がかかるといわれますが、昨今は、このような海外遠征に非常に大きな費用が必要になる時代になりました。
中央競技団体としては、予約や代金支払いだけでなく、経費精算、経理会計処理など、膨大な事務負担を行っています。それぞれの経費精算がどの補助金に結びついているかなども正確に整理していく必要もありますし、1つ1つの経費利用が中央競技団体内の政治問題になることもありますので、中央競技団体の経理は精神的な緊張もあり、意外と激務です。
2.意外と忙しない海外遠征
日本代表選手は国際大会に出場する際、大会期間中のオフの行動などをソーシャルメディアにアップすることも増えたため、国際大会などの海外遠征中、比較的時間があるようにも見えます。優雅に海外旅行しているように見えるかもしれません。
ただ、海外滞在期間中のオフはさておき、日本代表活動期間中の移動については割と忙しなく動いています。理由はもちろん移動や宿泊の費用をできる限り抑えるためで、日本代表活動期間について、余裕のある日数滞在しているケースはあまり見られません。オリンピックパラリンピックでも選手村にいつまでも滞在しているわけではなく、決められた滞在期間が終了すれば、他の選手のために選手村の宿泊施設を明け渡す必要があるので、選手村を出ることになります。
また、国際大会最終日まで勝ち上がり現地に滞在できればハッピーですが、早期に敗退すれば、早々に日本に帰国することになります。日本代表チームの選手やスタッフが1日長く滞在すれば、その分の費用は当然かかりますので、必要最小限の滞在で帰国の途に就くことになります。中には、現地夜の試合にて敗退した場合、夜中に滞在先のホテルに戻り、翌朝の飛行機で帰国するために、夜が明ける前に空港に向かっていることなどもあります(翌日の飛行機になってしまいますと、その全員分の滞在費用が必要になります)。オリンピックパラリンピックやワールドカップなどの激闘を終えた後、日本代表選手らが敗退した心の空白を埋める間もなく(実際寝る間もなく)、帰国の途についていることもよくあります。むしろ大会終了後オフが含まれることの方がレアでしょう。
3.ビジネス利用は当たり前?
日本代表活動の場合、飛行機移動がビジネスクラスなのかという話題があります。オリンピックにおいて、日本代表選手からメダルを取ったのに、帰国の際にビジネスクラスでなかったなどの意見が出ることもあります。
ただ、日本代表の実態としては、ほとんどの競技の移動でビジネスクラス利用はないのが実情です。もちろんビジネスクラス利用には大きな費用が必要になりますし、なかなかこのような費用を工面できる競技は限られています。日本代表の海外遠征においては、エコノミークラスで移動していることが一般的ですし、一部選手やスタッフが利用することがあっても、多くがエコノミークラスで移動しています。
もっとも、日本の場合、欧米から離れた極東地域にあるため、海外遠征で海外に行く場合も、海外でプレーする選手が日本に帰国する場合も、基本的に長距離の移動が前提になります。近年は、プロアマ問わず、試合日程が過密になってきており、移動時のコンディション調整が重要になってくる場合、必然的にビジネスクラス利用を検討する必要も出てきています。もちろん予算との兼ね合いですが、中央競技団体としても、海外でプレーする選手を中心に検討しなければならない課題になってきています。
4.チャーター便はどんなときに利用?
また、日本代表の活動でチャーター便が利用されたなどのニュースが出ることがあります。野球のWBC日本代表などは、WBC大会側が日本とアメリカ合衆国の往復についてチャーター便を用意しているので、確かにチャーター便で往復していたりします。最近は、サッカー日本代表チームの移動について、チャーター便利用がニュースになっていました。
一般の旅客便ですと、日本代表選手だからといってあまり特別扱いされるわけではありません。一般のお客さんと同じようにチェックインし、荷物検査を行い、搭乗口から一緒に飛行機に搭乗することになります。フライト中は、他のお客さんと同様にサービスが行われ、日本代表選手らだけが特別扱いを受けるわけではありません。一方、チャーター便の場合は、その便には日本代表選手らとスタッフしか搭乗しませんから、チェックイン、荷物検査や搭乗を全く別のルートから手配することも可能だったりします。試合終了後、すぐに移動した方が選手への負担も少なかったりしますので、試合会場から直接飛行機横までバスで移動し、様々な手続きをその場で済ませて搭乗することもあります。フライト中のサービスも、日本代表選手らとスタッフ向けに特注することもできますし、また一般のお客さんがいないので、貸し切り空間として自由な行動ができたりします。その意味で、日本代表が国際大会に出場するにあたり、チャーター便はとても利便性が高いです。
ただ、チャーター便というのも、口で言うのは簡単ですが、1つの便を、日本とアメリカ間や、日本と欧州間を飛ばすだけで、非常に大きな費用がかかります。また、野球のWBC日本代表のように往復が同じ行程であればあまり苦労はしませんが、サッカー日本代表であれば、ホームとアウェイの試合会場を双方移動するため、往復が同じ行程になるわけではありません。このような移動に対応するチャーター便を手配するとなると、様々な調整が必要になるため、現場スタッフが苦労していることもあります。ですので、チャーター便は、費用としても人手としてもなかなか大変な移動手段だったりします。
5.空港到着ロビー帰国風景の実際
国際大会を終えて日本に帰国した場合、空港の到着ロビーを通過する日本代表選手が報道されることがよくあります。オリンピックやワールドカップなどでの活躍の場合、数百人のファンが到着ロビーに押し寄せることになります。空港の到着ロビーは、もちろん他の便に乗られていたお客さんがおられますし、日本代表専用になっているわけではありません。そこで、実際到着ロビーの通過に関してはいろいろマネジメントがなされています。
一般のお客さんが少ない時間を狙って、日本代表選手がまとめて到着ロビーに出ていくこともあります。報道側としても、日本代表選手が通過するタイミングはまとめて出てきてもらった方が撮影もしやすく、また一般のお客さんのプライバシーにも配慮できるので、このような方法がとられます。税関側から見ていると日本代表選手が到着ロビーに出ていくタイミングを待っているケースもあり、空港もいろいろな配慮をしていることが感じられます。
また、多くのファンが押し寄せている場合、日本代表選手が通過するルートを一般のお客さんとは完全に別にしている場合もあります。空港がかなり混乱しますので、ファンや報道陣の配置を考え、空港内の余裕のあるスペースで実施されています。日本代表選手も一度到着ロビーを出て、一般のお客さんとは全く違う方向に進行し、ファンや報道陣の前を通過しています。中には、そのままバスなどに乗り込むのではなく、再度空港内の建物に入っていき、地下など別のスポットからバス移動しているケースなどもあります。
日本代表帰国後の到着ロビーのシーンは、皆さんもいろいろな大会について記憶されていることが多いかと思われますが、そのシーンのためにも、様々なマネジメントがなされています。