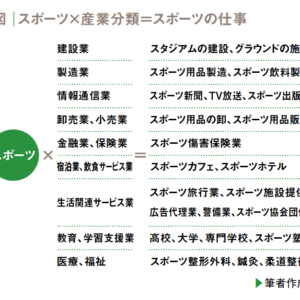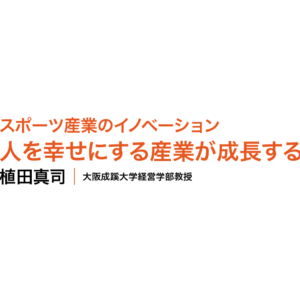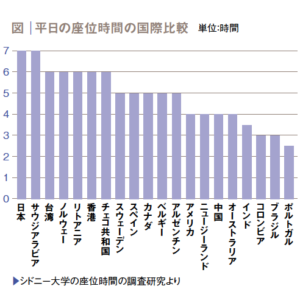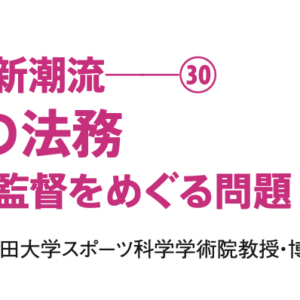ヴィリニュス定義3.0
Measuring the sports industry
ヴィリニュス定義3.0
庄子博人 同志社大学スポーツ健康科学部准教授
9月にパリとロンドンに出張しました。パリでは、パラリンピック開催期間中にヨーロッパスポーツマネジメント学会が開催され、学会に参加していたスポーツサテライトアカウント(SSA)やスポーツGDPを専門とする研究者と議論し、最新の動向を把握しました。ロンドンでは、英国のDCMS(デジタル・文化・メディア・スポーツ省)に対して、政策評価や立案にSSAやスポーツGDPがどのように活用されているかをインタビューしました。これらのインタビューで、新しいSSAに関する進展について知見を得ることができました。
SSAの最新動向
SSAに関しては、シェフィールド・ハラム大学スポーツ産業リサーチセンター(SIRC)のDr. テミス・ココラカキス氏と、民間調査会社econmoveのCEOでありスポーツ経済学者のDr. アンナ・クライスナー氏にインタビューを行いました。テミス氏は欧州のSSA開発の先駆者であり、英国および欧州全体のSSA開発に多大な貢献をしています。アンナ氏は、欧州全体のSSAやスポーツGDPの実際の計算を担当しており、2024年12月に公表予定の欧州SSAの最新バージョンを手掛けています。
両氏は共同研究として、学会でSSAに関する研究発表行っており、インタビューや学会発表から得られた最も重要なことは、SSAの枠組みを定義するヴィリニュス定義のアップデートが進められているということです。SSAは、2006年以降、ヴィリニュス定義に基づいて開発され、スポーツ関連の経済活動を分類する指針を提供してきました。この定義は2012年に大幅な改訂が行われ、現在はバージョン2となっています。バージョン2では、スポーツに関連する財・サービスを「統計的定義(コア)」「狭義の定義」「広義の定義」の3つに分類していますが、この方法には観光など他のサテライトアカウントとの方法論上の整合性が取れないという課題がありました。そのため、ヴィリニュス定義のバージョン3では、新たに「特徴財(Characteristic goods)」と「連携財(Connected goods)」という概念が導入され、従来のコア、狭義、広義の定義に代わるものとして位置づけられました。これらの「goods」という用語にはサービスも含まれており、特徴財にはスポーツサービスやスポーツ教育など、スポーツへの直接的な参加に関連する財・サービスが含まれます。さらに、スポーツに関わる消費行動を「アクティブ(Active)」と「パッシブ(Passive)」に分類し、スポーツへの投資がもたらす社会的リターンを正しく評価できる基準が導入されました。この新しいバージョンのSSAの結果は、定義の内容および欧州諸国における計算をまとめたレポートとして、12月に公表される予定です。
英国DCMSによる
SSAの政策評価
英国のDCMSは、新しいバージョンのSSA手法をいち早く採用しており、欧州諸国のレポートが12月に公表されるのに先駆け、9月には英国単独のレポートが発表される予定です。今回のインタビューでは、研究者への聞き取りとは異なる視点から、政策立案や政策評価においてSSAがどのように活用されているかをメインに伺いました。
DCMSは、上記でインタビューしたシェフィールド・ハラム大学のテミス氏らと共同で、新しいSSAの開発を進めてきたそうです。この新SSAは、ヴィリニス定義3.0に基づき、国単位で発表される初のレポートとなります。また、DCMSの新SSAは、マクロ統計としてのスポーツGVA(≒スポーツGDP)は2018年と同様の扱いですが、今回は枠組みが変更されるため、合計値の経年変化に加えて、地域やスポーツごとによる詳細な内容に焦点を当てているとのことです。
SSAの政策活用と評価については、SSAの結果を基に、各地域やスポーツへの公的資金などの投資価値を示すことだそうです。さらに、国全体では、スポーツGVAよりもスポーツ雇用の方が高いことを述べていました。こうした状況を地域やスポーツごとに分析し、政策活用することも視野に入れているとのことです。
また、スポーツに関する消費とスポーツ参加率の関連性については、改修されたテニスコートにおいてレッスン料を無料にすることで参加率が向上するかどうかの調査を進めているとのことでした。
英国のSSAでは、経済計算に基づいた国全体のマクロ統計から、地域や特定の区分に応じた細分化が進められ、実際の政策立案や評価に活用されようとしていることが明らかになりました。これに対して、日本のSSAも、実際の政策に反映できるような枠組みで取り組む必要があると改めて感じました。