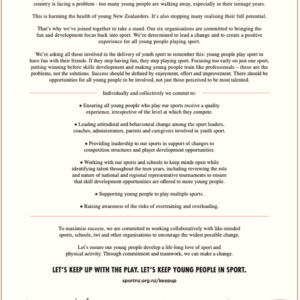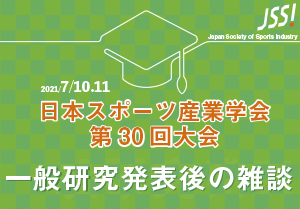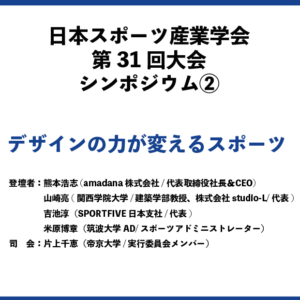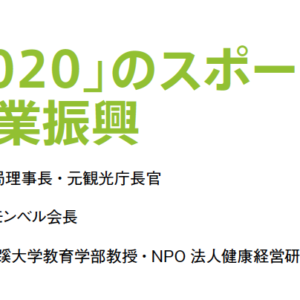「スポーツ産業」のこれまでとこれから
「スポーツ産業」のこれまでとこれから
日本スポーツ産業学会第34回大会が7月12日,13日にびわこ成蹊スポーツ大学で開催された。
初日に行われたシンポジウムの模様をお届けする。
1st session 「これまで」
庄子博人(同志社大学准教授)
尾山基(日本スポーツ産業学会会長/アシックス シニアアドバイザー)
35年間の振り返り(庄子博人)
まず私からはスポーツ産業学会が発足した1990年以降のトピックスについてお話しします。1990年に通商産業省から「スポーツビジョン21」が掲げられ、スポーツが基幹産業の一つと位置づけられました。。当時(1989年)のスポーツ市場規模は6兆4千億円で、2000年に20兆円と予測されていましたが、これは当時がバブル期の頂点であったことも背景にあります。以降は景気の動向に左右されて発展が難しかったのですが、2011年に「スポーツ基本法」第18条に「スポーツ産業」が明記されます。そうして日本再興戦略として「スポーツの成長産業化」やスポーツ未来開拓会議が設けられることでスポーツ産業政策は引き継がれていきました。
この35年で最も大きな変化は、日本国内に多くのプロリーグが誕生したことになります。1993年にJリーグがスタートし、2015年のBリーグ、2017年のTリーグと続き、また新たな動きとしてeスポーツやダンスが始まっています。多くの競技や種目でプロスポーツリーグが催され、親会社依存の「プロ野球型ビジネス」から自立した運営を目指す流れが加速しました。
それらの大きな要因には、財源・ファイナンスの変化があります。2001年にスポーツ振興くじのtotoによる助成がスタートし、近年では年間100〜200億円がスポーツに還元されています。また、ふるさと納税やクラウドファンディングによる寄付でスポーツ界に財源を集めることが可能になりました。さらには公共プロジェクトに民間資金が活用されるようになったことも変化の一つです。PFI法の制定(1999年)、地方自治法の改正(2003年)などによって、スタジアムやアリーナへの民間資金の活用が起きました。
この35年間、日本では様々な世界的スポーツイベントが開催され、それらに際して、スポーツ中継のライブ配信も増加しました。
ほかにもスポーツに関する政策の変化があります。全国の市町村に一つ以上の総合型地域スポーツクラブを設置する動きが始まりました。その目標を現在ほぼ達成し、十分に管理が届いている地域スポーツの担い手と言えるクラブも存在します。ですが、財源やクラブマネジャーの不足、クラブの会員数など多くの問題もあります。同時に、社会資本としてのスポーツ施設はこの35年間で大きく減少しました。スタジアムやアリーナの改革に際してスポーツ関連施設の質の向上や官民連携によるファイナンス面の発展は見られるものの、その一方で学校の統廃合の影響などから地域スポーツを担う社会資本は減少していることが特徴となります。
スポーツ産業に関して経済規模の変化に目を向けると、2019年のスポーツGDPは9.3兆円、対GDP比は1.67%でした。国内の産業全体と比較してもスポーツ産業の成長率の高さを意味しており、とりわけ「スポーツ施設」「スポーツ関連の流通業」「スポーツ教育」の3つの分野がおよそ半分以上の経済規模を占めています。ですが、そうした内需主導型のスポーツ産業も、成長率でいえばこの10年間はそれほど伸びておりません。これは社会資本としてのスポーツ施設の減少を踏まえれば当然の結果と言えます。
対して近年の成長分野は外需型の産業であり、インバウンドスポーツツーリズムに代表されるような成長トレンドや大手メーカーによるグローバル市場を見据えた販売戦略がその主たるものに該当します。またスポーツ産業という観点からすれば、法人化されていない任意団体がまだまだ数多く存在することは、スポーツGDPとしての生産性の付加価値をカウントできない問題を生んでいます。近年は学生団体が法人化を取得するような事例もあり、付加価値の主体さらには産業の主役として任意団体から法人化するスポーツ組織を増やしていく必要があるかどうかは議論の余地があると考えます。
アシックス社のグローバル戦略について(尾山基)
私はオランダで勤務し、2008年に社長になりましたが、それより以前からアシックスでは社内の共通語を日本語と英語にしていました。これによって、デジタル、開発、生産、販売、マーケティングを両方の言語で回すことができるわけです。何より人手不足はまるで関係なく、実際に私が社長の時代にも神戸本社には26カ国以上の人間がいました。大きなポイントだったと感じます。
世界的なスポーツブランドを挙げますと、最大手はNIKE社になります。もっとも、NIKE社が発展した背景には、アメリカというスポーツ大国ならではの市場規模の大きさがあると思います。さらには、バスケットボールのマイケル・ジョーダンと特別な契約を結ぶという画期的なモデルケースに代表されるように、スポーツマーケティング先行で商品がある点も大きいでしょう。NIKE社のスウォシュと同様に、アシックスとしても東京2020オリンピックに目掛けてロゴを変更しつつ、グローバルでブランドイメージをうまく展開していきました。
いま現在、アシックスはDXを活用しながら事業を進めています。2016年に、ボストンにあるランニングやフィットネスのアプリーケーション会社を買収しました。ただアメリカの人材はどうしても給与の高い地域に流れる傾向などもあるので、今後はクローズなAIを導入していくことも検討の余地があります。AIを導入すれば、拠点を限定する必要がなくなり、ネットワークを駆使すればどこでも事業を展開できます。
また、スポーツ業界に限らずインバウンドに頼った経済になっている点は私も危惧するところです。インバウンドに頼るのか、それともベースとなる事業があってインバウンドはあくまでもプラスアルファとする経営にするのか、それは考える必要があります。経営はアップダウンがあるものですが、人口の流動性はとても重要なキーワードです。
さらにはスポーツがカジュアル化していることも要点になります。高級時計のように物自体にバリューがあれば、それが資産となるわけですが、スポーツ用品はそうはならないと思います。かつて銀座にオニツカタイガーの店舗を構えたときには、外国人のお客様ばかりでしたが、「この人たちがいなくなったらどうなるんだ?」と不安を覚えたものです。とはいえ、海外との距離が縮まり国境の垣根が低くなった今、デフレやインフレの影響による購買の変化はさておき、「欲しいか、欲しくないか」という根本は変わりません。
また私がオニツカタイガーを手がけた際には、百貨店などへ卸売をせず、自分たちの手で販売をしていました。そうすることで、誘引される顧客はいると考えていましたので。そうした販売戦略に関する感性も求められるのではないかと思うところです。岡田氏 今回は「35年後のスポーツ産業」がテーマですが、非常に予測は難しいので、まずは直近の未来についてお話ししたいと思います。とりわけ議題に挙がるテクノロジーに関しては、将来を見据えたうえで欠かせません。AIを中心に、この先もテクノロジーによって様々なことがブレイクスルーを果たすでしょう。
スタジアムやアリーナをベースにして、興行面での成長はもちろんのこと、物販などにおけるデジタルサービスの導入やLEDなどの投影技術を用いた没入体験の深化は今後も変わっていくと思われます。また試合に関しても、「ホークアイ」に代表されるように即座に判定できるテクノロジーはすでに実装済みですし、データの取得や管理を行うデータスタジアムと言った会社においてもこれまでは作業員による手作業から自動化が進んでいます。
またテクノロジーを用いた発展系の一つとして、電子化したモノのマーケットも今後の焦点の一つになりえます。例えば、カード業界はビジネスモデルこそ変わっていませんが、例えばNFTはブロックチェーンのテクノロジーを活用して物理的な壁と時間的な壁をブレイクスルーしました。グローバルな経済と連携し、すでに電子上ではセカンドマーケットができあがっています。また、時間と競技の壁を越えたものとしては、スポーツベッティングも大きな産業として将来を考えた際には一つの入り口になります。
テクノロジー方面の話題以外で言えば、やはりオリンピックの在り方は欠かせません。1984年ロサンゼルス大会から始まったいわゆる“商業オリンピック”が昨年の2024年パリ大会まで発展してきたわけですが、その役割など本質的な部分が変わりつつあるとは皆さんも感じていらっしゃるはず。
オリンピックが変化する今、スポーツビジネスにおいては、それでもいかに人を集めてエンターテイメントを絡めて複合化させることで大きなサイクルを生むかを考える時代が到来したと言えます。その点で注目を集めるのが、サウジアラビアの「キディヤ・シティ」です。サウジアラビアはeスポーツの産業が育っており、またスポーツ施設とエンターテイメント施設を融合させた巨大なカルチャー系の施設をつくる構想を進めています。日本においては非現実と言われますが、財政面に関する様々な手立てを施して進めていくことが今後の検討材料になるでしょう。
2nd session 「これから」
藤沢久美(日本スポーツ産業学会理事長/国際社会経済研究所理事長)
間野義之(日本スポーツ産業学会理事、運営委員長/びわこ成蹊スポーツ大学教授 前学長)
岡田 明(EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)
藤沢氏 現在、世界中で様々な分断が起き、新しいグループに分かれ、世界の国境すら変えようという動きがあります。そういう時に、スポーツの力はやはり大事なのではないかとスポーツ産業を研究する一人として考えています。先ほど例にあがりました「ホークアイ」に関してもスポーツの分野でとても活躍しているテクノロジーですが、同時に武器産業でも世界でトップ5に入る収益を上げています。古代オリンピックは兵士によって争われていた、ということがスポーツの一つの要素だと考えれば、長い月日を経た今、「スポーツと闘い」という関係性を踏まえて現代では何が起きるのか。また、そこには必ず新しいテクノロジーが関わってきます。将来、世界で新しい国境線が引かれた時にスポーツがどのような役割を果たすのか。スポーツによって生み出された技術がいかに世界へインパクトを与えていくのか。それらを考えることがとても重要になります。
私自身、NECグループのシンクタンクとしてAIネイティブ化にチャレンジしています。AIだけでビジネスやサービスを作り出した際に、どれだけフィジカルつまり人間を使うかを図っており、今後このような企業が増えて社会が変化した際に、果たしてスポーツはどのような役割を担うのか。スポーツとエンターテイメントを掛け算する感情が、人間にどのような力を与えるのかを考えると、35年後はスポーツ産業も現在のような小さな規模ではなく、もっと人類を変えていく、場合によっては世界の平和を占う存在になるかもしれない。そんな視点も非常に興味深いところです。
間野氏 現在は第4次産業革命と言われており、間違いなく35年後の歴史の教科書にそのように書かれることでしょう。ですが、どれだけ科学が進歩しても、私たち生物としてのヒトの身体量、また睡眠と食事といった生命維持に必要な事象は変化していません。35年後もデジタル・テクノロジーは飛躍的に発展するかもしれませんが、生物としてのヒトはほとんど変わらないと思います。
しかし、一方で、数年前のヨーロッパスポーツマネジメント学会での「将来のスポーツビジネス」をテーマにした講演で「ゲノム編集ビジネス」の話題が出てきました。それはすなわちバイオテクノロジーやメディカルの分野へもスポーツビジネスが展開していくのではないか、ということです。具体的には、競技や体力維持に最適なゲノムを各人が選択し編集する時代がくるかも知れないということでした。今は自分たちの身体を定数、テクノロジーを変数として捉えているわけですが、身体も変数になっていくという可能性を示唆していました。
実際に、富裕層は不老不死のための技術を探し求め始めているそうです。老化がゆっくりと進み寿命が著しく延びたときに、スポーツの在り方はどうなるのか。今とはまるで異なるスポーツ産業も見えてくるかもしれません。それが35年後かどうかは定かではありませんが、第5次産業革命が起きる可能性も否定できません。
<質疑応答>
Q.スポーツ産業の定義や領域について今後の見立てはいかがでしょうか。
A.岡田氏 スポーツ産業全体に目を向ければ、今や産業自体の結びつきはとても密になってきています。エンターテイメントとして自由にチームを構想する『ファンタジースポーツ』でいえば、もともとは検証を主とした取り組みだったわけですが、今やメディアやデジタル分野と共同で展開されています。収益を生むための興味関心を引く一手として、ファンタジースポーツやスポーツベッティングが活用される。となれば、これはどの産業かという線引きが分からないとなるわけです。
A.間野氏 例えばスポーツ・ベッティングは今後の新領域だと思います。G7の国のなかで今、(スマートフォンなどによる)オンライン形式を取り入れていないのは日本だけで、他の諸外国では解禁されています。オンラインカジノの不法賭博が昨今は話題になっていますが、すでに海外のサイト等で違法に行われている日本人のスポーツ・ベッティングは5〜6兆円と言われています。それらを合法化して課税対象にし、学校の部活動の地域展開への財源に充てるなど、スポーツの新たな公的財源づくりが、スポーツ産業のさらに新しい領域をつくるかも知れません。
スポーツ・ベッティングは、法整備を含めて政治的な段取りが難しいものです。ギャンブル依存症と競技者の八百長の懸念があるので、それを解決しないことには導入できませんが、競技中の不正を防止するためのマコリン条約が制定され、多くの国が批准しています。日本としてはスポーツ・ベッティングを“鎖国”していますが、いつかは“開国”を迫られるでしょうから、今後35年のうちには導入することになるかも知れません。
Q.先般、「エンハウスドゲーム」というドーピングOKの大会が開催されました。また、男女の競技の境目など、世界ではインクルーシブな観点もスポーツには関わってくるようになりました。そこに対して、お考えをお聞かせください
A.間野氏 スポーツ産業は、「自由時間産業」に該当し、自由時間の遊びなので自由な発想が今後はさらに広がると思いますし、近代スポーツの枠組みに囚われない、より魅力的な仕組みを模索する必要があります。自由時間とは、24時間から睡眠・食事・通勤通学・就労就学等の生活必需時間を除いた時間のことで、調査によれば平日でおよそ4時間、休日で7時間と言われています。
この希少な自由時間市場をSNS・音楽・ゲームなど様々な娯楽と取り合い競争をしています。一人で停止と再生ができる音楽やゲームと違って、スポーツは同一時間に仲間をそろえて同じ場所に集まる必要がある。スポーツは最も難しい“自由時間商品”と言えるでしょう。自由時間産業での競争がどんどん激しくなっていったときに、e-スポーツのようにオンライン化も含めて、スポーツそれ自体も変容するのではないかと考えます。
A.藤沢氏 スポーツの定義自体についても言えますよね。例えば、今ではジムを利用する方々は重い重量を上げていますが、昔はそれも仕事で、わざわざジムに行く人はいなかったわけです。現在の第4次産業革命において、AIがものすごいスピード革命の一つと考えた際に、スポーツの定義も変わるのではないかと思います。
過去をしっかりと学ぶことは必要ですが、未来について発信することで進歩できるのも確かです。『どんな未来を誰が作ってくれるのかな?』ではなく、是非、教育現場の方々には学生の皆さんと一緒に『どんな未来であれば人類は幸せなのか』という観点でデザインしていただければありがたいです。