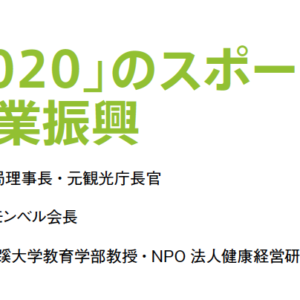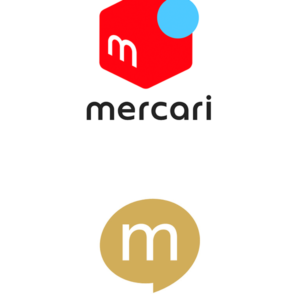「スポーツ産業学研究」のこれから
「スポーツ産業学研究」のこれから
パネリスト:舟橋弘晃(中京大学准教授/「スポーツ産業学研究」編集委員)
小木曽湧(東洋大学助教/同)×ファシリテーター:菅文彦(大阪成蹊大学教授)
本シンポジウムでは、パネリストに加え、会場フロアの若手中堅研究者もコメント参画。スポーツ産業の急速な変容を踏まえ、「スポーツ産業学研究がこれから何をなすべきか」を中心に、産業構造変容・研究者と現場の関係性・学会の役割などについて多角的な議論が展開された。ここではその様子をレポート形式でお伝えする。
議論の基点となったのは「スポーツそのものの定義が揺らいでいる」という指摘である。生身の人間の身体能力は今後大幅には伸びない一方、テクノロジーの進展により、身体拡張技術や超人スポーツ、さらにはAI/バーチャル空間での競技の発展など、“スポーツの形態が多様化し続ける未来”が現実味を帯びていることが示された。
初音ミクのライブに象徴されるように、非人間的存在への感情移入も一般化しつつあり、スポーツでもアバター競技・ロボット競技が成立する可能性が語られ、「スポーツの変容を前提にした産業研究」が必要であるという問題意識が会場に広がった。
次に、スポーツ産業の構造変化として、「スポーツ×他領域(観光・健康・テクノロジー等)の掛け算による市場拡大」が急速に進む現状が紹介された。スポーツ単体ではなく、多産業との融合によってウェルビーイングやサステナビリティに寄与する“総合産業”へ移行するという見通しが示され、スポーツ産業学研究はその広がりを捉えるべきだという認識が共有された。
研究テーマの選択については、論文競争市場の構造を踏まえ、「学会がテーマを誘導しすぎるリスク」も議論された。特定テーマへの偏りにより他領域の研究が停滞する可能性が指摘され、
・研究者は社会的ニーズを感じ取りつつ、自身の価値観に基づくボトムアップのテーマ選択が重要
・学会は“方向付けすぎない”慎重さが必要
という意見が提示された。
現場の課題や社会的ニーズからテーマを見出すべきとの声も多く、特に政策領域との接続、現場の困りごとを出発点とした研究の重要性が強調された。研究者の中には「政策→研究テーマ→学術意義の後付け」というスタイルを意識的に取っている者もおり、学会の特性として“現実の問題解決志向”が通底していることがわかった。
議論の後半では、現場と研究者の溝が改めて浮き彫りになった。現場側からは「頼れる相手がいない」「論文化のノウハウ不足」という切実な声が上がり、
・相談窓口(アドバイザー制度)
・産学共同プラットフォーム
・リーグとの連携による研究会の開催
などの具体的提案がなされた。編集委員会側も、ケーススタディ等の“現場知”をもっと受理できる枠組みの整備の必要性を認め、1例報告を含む柔軟な掲載形式を模索していることが示された。
実務家教員からは「研究者と実務家をつなぐハブになる存在の育成」を学会が支援すべきとの提案があり、若手研究者と現場を結び付けるマッチングの可能性も示された。現場の困りごとを起点とした研究事例は、まさに当学会の強みであり、こうした知の循環を促進する仕組み作りが求められている。
また、VR観戦の社会実装の難しさなどが共有され、
「研究者だけでは実装できず、現場だけでも進まない」
「産業横断のプラットフォームこそが必要」
という認識が広く共有された。
最後に、AIがスポーツの本質に与える影響についての危機意識も提示され、AIによる競技構造の変質や、ルール形成や勝敗基準の再編が必然的に起こるとし、「スポーツ産業学こそがこの急速な変化に対処すべき」と強調された。
本シンポジウムを通して、スポーツ産業学研究の方向性として次の3点が明確となった。
1.スポーツの本質的変容(身体・AI・バーチャル)を前提にした研究の必要性
2.産業横断の“スポーツ×他領域”を捉える学際的研究の推進
3.現場と研究者をつなぐ制度設計(相談窓口・共同研究プラットフォーム)の構築
これらはすべて、スポーツ産業の発展と社会実装に直結する”日本スポーツ産業学会ならではの使命”として位置づけられた。