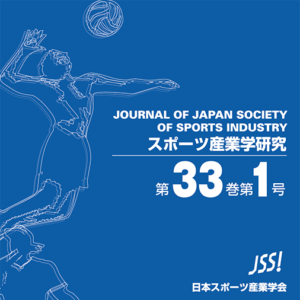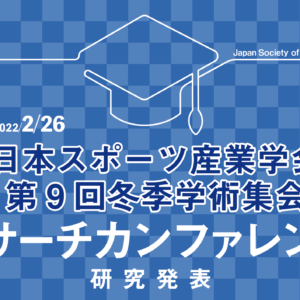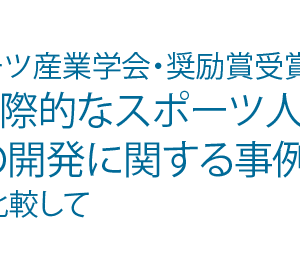スポーツ産業学研究第35巻第1号
【原著論文】
マイクロフォンによる卓球ボールの位置推定
川久保峻,伊藤建一,上島慶
JSTAGE
引退前の活動が指導者以外の職業選択に与えた影響について:JFL退団選手サブ・エリートとノン・エリートに着目して
赤星佐和子,澤井和彦,小木曽湧,間野義之
JSTAGE
Bリーグ観戦者の消費行動を予測する多重要因モデル:観戦動機,チーム・アイデンティフィケーション,ゲーム魅力,施設要因
元晶煜,Sungick MIN,Kerry FISCHER,Eunseo (Cloe) WON,Kevin K. BYON
JSTAGE
【研究ノート】
ヘルスリテラシーの観点から考える学校における月経教育のあり方
伊藤 華英,山中恕,最上紘太,小塩靖崇
JSTAGE
【レイサマリー】
マイクロフォンによる卓球ボールの位置推定
川久保峻(新潟工科大学),伊藤建一(新潟工科大学),上島慶(新潟工科大学)
今日の競技スポーツでは,科学的なデータ収集による客観的分析が競技力を向上させる上で重要になってきています.特に対戦型の球技種目においては,対戦相手の配球パターンやプレーの特徴をあらかじめ分析しておくことが試合に向けた準備として有効になります.このようなデータの収集方法としては,カメラなどの映像技術を用いたものが広く使われています.また,近年では,従来のハイスピードカメラを用いた手法だけでなく,新たな機器を使った研究が進められています.球技種目においての研究は従来から行われており,その分析方法も進化を遂げてきていますが,卓球の技術・戦術分析手法に関しては様々な課題が残っています.卓球競技の場合,競技で使用されるボールが他の球技よりも小さく,ラリーのスピードが非常に高速であるためにラリーを映像で捉えにくく,即時的な分析が困難であるといったことが挙げられます.そのため,卓球競技においては,他球技と比べて,打球ボールの落下位置や,ラケットの位置などをリアルタイムで分析するシステムの開発が進んでいませんでした.
筆者らは,ボールが卓球台へ落下した際の振動解析から卓球ボールの落下位置を推定し,卓球の技術・戦術を分析するシステムの開発に取り組んでいます.当研究室の先行研究では,アコースティックエミッション信号の振幅から時間差情報を用いて,落下座標を推定する方法を検証しました.しかし,この手法は,卓球台の不均一性から振動波の伝搬速度が一様ではなく,ボールの落下位置を推定することは困難でした.
そこで,本研究では,以前,電波源の位置推定の研究行った経験から同じ空間を伝わる音波に着目し,マイクロフォンを使用する手法で,ボールの落下・打球位置を推定できるか検証しました.具体的には,ボールの自由落下およびラリーによる計測・解析において落下・打球の位置推定精度を検証しました.検証の結果,自由落下における卓球ボールの位置推定では,誤差1~4cm程度で推定できることが確認できました.また,ラリーにおける検証についても,落下位置は自由落下の検証と同程度の誤差で推定可能であることが確認されました.ラケット打球位置については,10~20cm程度の誤差が確認されたもののおおよそのインパクト位置を把握できることが示されました.今後は,即時的な位置推定と技術・戦術分析システムの有用性を高めていくことが課題となります.
引退前の活動が指導者以外の職業選択に与えた影響について:JFL退団選手サブ・エリートとノン・エリートに着目して
赤星 佐和子(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科)
澤井 和彦(明治大学商学部)
小木曽 湧(東洋大学健康スポーツ科学部)
間野 義之(びわこ成蹊スポーツ大学)
スポーツ選手の競技人生において避けて通れないのが「引退」である。JOC(日本オリンピック委員会)の無料職業紹介事業「アスナビ」や日本プロサッカー選手会(JPFA)による就学支援金制度など、オリンピックを目指すトップアスリートやプロスポーツ選手へのキャリア支援は少しずつではあるが、着実に整備されつつある。一方で、プロの直下に位置するいわゆるセミプロの選手の中には、競技しながら働いている者も多くいる。これらのアスリートに対するキャリア支援は、現時点で十分に整備されているようには見えない。
そこで本研究は、セミプロアスリートのキャリアトランジションにおいて、引退前にどのような活動や準備が行われているかを探索的に検討した。具体的には、Jリーグの直下に位置するアマチュア最上位リーグのJFL(日本フットボールリーグ)退団選手に焦点を当て、セカンドキャリアを視野にどのような活動を行い、競技関連職以外の職業選択にどのような影響を与えているのかを検討した。
JFLクラブを5年以内(2018年~2023年)に退団した選手で、競技関連職以外の仕事に就いた11名を研究対象とした。競技引退前からセカンドキャリア選択まで時系列に沿って、現役中の具体的な活動内容、引退理由、引退後の職業選択についてインタビュー調査を実施した。
JFLは雇用環境や競技レベルなど多様な選手が混在したアマチュアリーグで、彼らの中には中学年代、高校年代にJリーグ上位クラブの下部組織に所属していた者や、高校の全国大会で上位の成績を残した者など、一定の競技レベルと競技キャリアを送ってきた者も多い。一方で、アマチュアリーグとしての性質上、目立った競技実績はなく高いレベルでの競技を志向して参加している選手も含まれている。
そこで本研究では、前者を「サブ・エリート」、後者を「ノン・エリート」と定義して、競技への向き合い方や競技レベル、クラブでの待遇によってキャリア移行期に抱える課題や職業選択時に活用している資源の共通点および違いを把握しようと考えた。
インタビュー調査と分析の結果、両者とも引退前の活動については「競技以外の人との関係づくり」「就業経験」といった選手の行動特性が明らかになった。これらの経験を通じて現役中に次のキャリアや自分の適職を摸索しており、「競技以外の時間の使い方」が引退後の職業選択に影響を与えていることが明らかにされた。
本研究の結果から、「働けるリーグ」であることをクラブとセミプロアスリート双方がポジティブに捉え、企業で働く上での心構えやビジネスマナーを習得する講習会をクラブやリーグが主催するなど、選手の社会人基礎力の向上を目的とする施策と、競技関連以外の業界で働く人との接点づくりをクラブのスケジュールに組み込むことが有効なのではないかと考えられる。
Bリーグ観戦者の消費行動を予測する多重要因モデル
元 晶煜(愛知大学)
Sungick MIN(ニューヨーク州立大学フレドニア校)
Kerry FISCHER(ニューヨーク州立大学フレドニア校)
Eunseo (Cloe) WON(ジョンス・ホプキンズ大学)
Kevin K. BYON(インディアナ大学ブルーミントン校)
スポーツ観戦動機は, スポーツファンが観戦行動を行う動因(spectator motives)を意味します.そうすると, 様々な観戦動機(原因)と観戦者の消費行動(結果)の間には, 因果関係が成立します. しかし, Funk et al.(2009), Kim et al.(2011), Trail et al.(2023) などが指摘するように, 既存の観戦動機研究において, 観戦動機が観戦者の消費行動(特に観戦回数)を説明する説明率(重回帰分析における決定係数R2)は低い水準であります.本研究は,この課題に着目し,従来のスポーツ観戦動機モデル(Won & Kitamura, 2006)にゲーム魅力(game attractiveness)と施設 (facility)の変数を加えた多重要因モデルを提案し, そのための尺度項目の改良を行ったうえで, そのモデルを検証しました.
本研究の目的は, Bリーグ観戦者の消費行動(観戦回数,将来の観戦とマーチャンダイジング商品購入への意図)を説明する多重要因モデルを提案することでありました.そのための研究方法としては,まず関連する文献のレビューを行った結果,Bリーグ観戦者の消費行動は4つの要因(観戦動機,チーム・アイデンティフィケーション,ゲーム魅力,施設要因)の相互作用で説明できるという研究仮説を立てました.その仮説を検証するために,Bリーグの観戦者を対象に質問紙調査を行いました.
研究の結果,本研究で提示した多重要因モデルは,(1)構成概念や尺度項目に信頼性と妥当性が確認され,(2)Bリーグ対象者の観戦回数変量の42%が説明でき,将来の消費意図変量の79%を説明できることが明らかになりました.また,(3)娯楽(entertainment)動機が観戦回数を最も説明しており,ゲーム魅力(game attractiveness)は新たな因子として確認された.さらに,(4)チーム・アイデンティフィケーションが将来の消費意図を説明する決定的な要因であることも明らかになりました.
本研究の結果,従来の観戦動機モデルに,先行研究で関連性が確認されている様々な変数を含めた多次元の複合モデルが,スポーツ観戦者の消費行動をより説明できることが示唆されました.今後も複数の要因による複合モデルを様々なプロスポーツの消費者を対象に検証していきたいと思います.
ヘルスリテラシーの観点から考える学校における月経教育のあり方
伊藤 華英(一般社団法人スポーツを止めるな)
山中 恕(大阪産業大学スポーツ健康学部)
最上 紘太(一般社団法人スポーツを止めるな)
小塩 靖崇(国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部)
研究背景:月経は、女性の健康と日常生活に深く関わる生理現象である。月経痛や過度の出血といった状態は、学業成績や運動パフォーマンスに支障をきたす。月経に関する理解が十分でない場合には、適切な対処が難しくなり、健康状態の悪化にもつながり得る。また、月経に対する誤解や偏見は、女性が助けを求めることをためらう原因となり、精神的負担を増大させる。しかし、月経に関する話題は依然としてタブー視されることが多く、正確な知識や適切な対処法が十分に浸透していないのが現状である。学校教育は、若者が月経について正しい知識を得て、自身の健康を管理する力を養う上で重要な役割を果たしている。現在の学校における月経教育は、学習指導要領に基づいて小学校から高等学校まで段階的に実施されているものの、その内容は主に生物学的メカニズムといった機能的ヘルスリテラシーに焦点を当てており、相互作用的および批判的ヘルスリテラシーの観点が欠如していると考えられる。
研究目的:本研究は、月経に関するヘルスリテラシー(menstrual health literacy)*向上のため、学校教育の改善案の提案を目的とする。また、批判的ヘルスリテラシーの向上を目指した授業実践を議論するため,スポーツ界で月経に関する障壁を経験したアスリートのエピソードを活用した教育実践例として「1252プロジェクト」の取り組みを紹介し、社会的偏見の解消と支援的な環境構築に向けた具体案を示す。
方法①文献調査:月経教育プログラムの効果検証を目的とした研究11件をシステマティックレビューに基づいて精査した。各プログラムの実施内容、効果測定方法、対象者の特徴を「機能的ヘルスリテラシー」「相互作用的ヘルスリテラシー」「批判的ヘルスリテラシー」の観点から分類し、その有効性を分析した。
方法②国内事例の分析:1252プロジェクトが高校およびスポーツチームで実施した教育内容を調査し、教育効果や参加者の反応を整理した。特に、アスリートの経験を活用した教育の特徴とその影響を詳細に検討した。
結果①文献調査:11件のすべてにおいて、月経に関する知識向上が確認され、その多くで健康行動への態度改善も見られた。しかし、批判的ヘルスリテラシーを扱うプログラムはほとんど存在しなかった。グループ討論や視覚教材の活用が効果的であり、参加型学習が知識の定着と行動変容を促すことが示唆された。
結果②1252プロジェクトの実践:高校での実践では、元アスリートによる経験談やクイズ形式の参加型授業を通じ、生徒が月経に関する知識を深めるとともに、話し合いや意見交換を通じて社会的な理解を広げる活動を行った。また、スポーツチームでは、選手間の情報共有や指導者との意見交換を促進することで、月経に関するオープンなコミュニケーションの環境を構築した。特に、生徒主導の活動が、月経に関する偏見を軽減し、行動変容につながる可能性が示された。
結果から言えること:日本の学校教育における月経教育は、主に機能的ヘルスリテラシーに重点が置いているが、社会的課題に対処するための相互作用的および批判的ヘルスリテラシーが不足している。本研究では、「1252プロジェクト」を参考にした教育手法を提案し、生徒自身が主体的に月経について学ぶだけでなく、学校全体や地域社会の環境改善を目指す必要性を指摘した。特に、アスリートの経験を活用した教育は、月経に対する偏見を取り除き、性別を問わず全ての人々が月経を理解し支援する社会を構築する有効な手段である。今後は、これらの教育プログラムを実施し、長期的な効果を検証するとともに、学校教育全体におけるヘルスリテラシー向上のための包括的な取り組みが求められる。
*月経に関するヘルスリテラシーとは、月経に関連する情報を入手し、理解し、適切に活用する能力およびスキルを指し、具体的な分類として、以下の三つの領域から構成される。「機能的ヘルスリテラシー:基本的な読み書き能力を基盤とし、健康情報を理解する力」「相互作用的ヘルスリテラシー:周囲の人々とコミュニケーションをとりながら、サポーティブな環境の中で情報を活用し行動する力」「批判的ヘルスリテラシー:情報を分析的に捉え、自らの環境を改善するための社会参加能力」