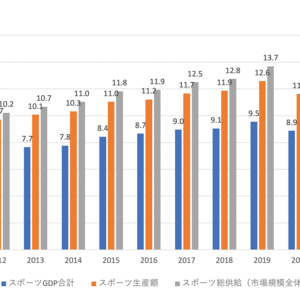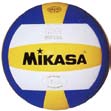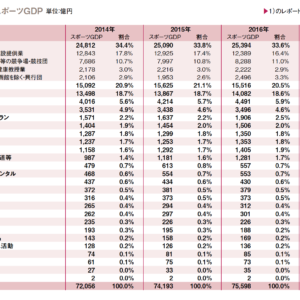学生アスリート増加の背景とは?
アスリートの教育とキャリア形成③
学生アスリート増加の背景とは?
帝京大学 束原文郎
連載「アスリートの教育とキャリア形成」、第3回は第2回に続き私立大学における体育・スポーツ・健康系学部の入学者動向をもとに、学生アスリートのマーケット規模を考える。
図1には、体育・スポーツ・健康系学部の学部別入学者数および定員充足率の推移(2011〜2024)をまとめた。ここから指摘できるのは、体育・スポーツ健康系学部が大学入学者全体に対するシェアを伸ばしてきているということだ。13年間で0.7%程度の微々たる上昇に見えるが、縮小するマーケットの中で3,000〜4,000人規模で入学者数を伸ばしたことは特筆に値しよう。
しかしながら、体育学部は入学者数および定員充足率をともに減少させている。2011年には5,352人いた入学者数が2024年には4,579人となり、充足率も120.5%から98.1%へ、20ポイント以上の減少となっている。また、入学者数は増やしたものの、キャパシティに対する充足率を大幅に減少させたのは、健康科学部および健康福祉学部である。その入学者数は体育・スポーツ・健康系全体の2024年度入学者数15,659の31%と、依然として大きな部分を占めるが、定員を増やしすぎたのか、充足率は24年度に88%まで落ち込んでいる。体育・スポーツ・健康系学部の定員充足率の減少の主因は、健康科学部および健康福祉学部の大幅縮小にあったことになる。
縮小傾向の中で唯一好調なのが、スポーツ科学部をはじめ学部名に「スポーツ」を含む学部である。2011年当初には体育・スポーツ・健康系学部の傍流であったのが徐々にそのシェアを拡大し、23年には体育学部を超えて入学者数、定員充足率ともに同系のトップに躍進した。いわば、「体育・健康からスポーツへ」、という傾向が生じたと言える。
ただし、前回も確認した通り、『私立大学学生生活白書2022』によれば、2021年調査時点で「体育会の活動」に参加している私大生は体育・スポーツ系学部で約2/3(66.5%)である。今回わかったのは体育・スポーツ・健康系学部入学者は全国で15,600名余り。これの3分の2が体育・スポーツ・健康系学部入学者中の体育会アスリートと考えると、その数はおよそ10,000名足らずということになる。
他方、同白書2021年調査時点の私学生全体の「体育会の活動」参加者は28.6%である。私学全体の学生数は文科省『学校基本調査』より2,177,756人、1学年分はこれの1/4、つまり544,439人、さらにこの28.6%≒155,710人が体育会活動参加者と想定される。体育・スポーツ・健康系学部の増加は確かに体育会系の増加に寄与はしているが、シェアで言うと15〜16分の1程度の規模になる。
ちなみに2024年度の国立大生は約60万人、1学年は約15万人である。国立大生の何割が学生アスリートとして活動しているかわからないため、体育会学生限定の就職支援事業を展開する㈱アスリートプランニングのサービス利用者の国公立:私立比から推計する。するとその比はおよそ約1:9だった(束原ほか、2024)。ここから、国立大アスリートは少なくとも私立大の10分の1程度、15,000人程度と想定すると、学生全体では1学年はおよそ17〜18万人、4学年で少なく見積もっても約60万人が体育会アスリートであると考えることができる。
【参考文献】束原文郎, 横田匡俊, 石川勝彦, 幸野邦男, 宮﨑亜美, 岡本円香, 児子千夏 (2024) 学生アスリートの競技への取組方は人気企業からの内定獲得に影響するか?. 体育学研究, 69, 389-406.