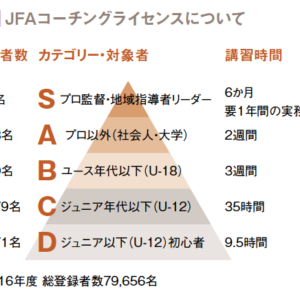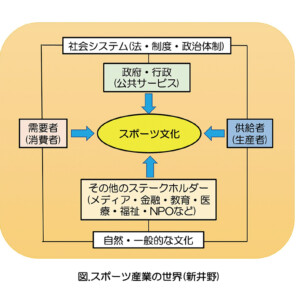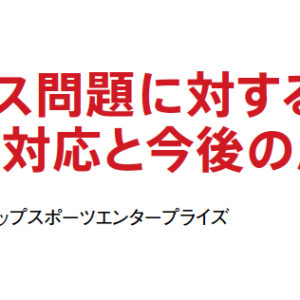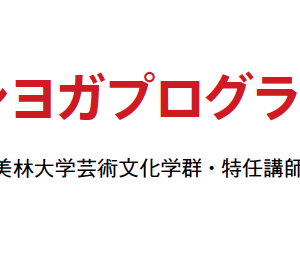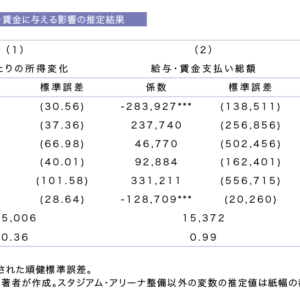プロスポーツクラブ経営におけるパートナーシップ形成・強化要因の質的分析: オフィシャルパートナー企業の意思決定プロセスに注目して
プロスポーツクラブ経営におけるパートナーシップ形成・強化要因の質的分析:
オフィシャルパートナー企業の意思決定プロセスに注目して
新潟医療福祉大学 健康科学部 山本悦史
立命館大学 産業社会学部 中西純司
この度は,令和6年度学会賞という栄誉ある賞を授与していただき,誠に有り難うございます.また,受賞論文について解説を行う機会をいただき,関係者の皆様に心より感謝申し上げます.以下では,受賞論文の概要についてご説明いたします.
研究の背景および目的
近年,スポンサーシップアクティベーションやSDGs,ESG,サステナビリティなどをキーワードとしながら,プロスポーツクラブと企業との持続可能なパートナーシップのあり方が活発に議論されるようになっています.また,サッカーJリーグに加盟するプロサッカークラブ(以下「Jクラブ」とします)の営業収益に対する広告料収入の割合が,その他の項目(入場料収入やJリーグ配分金,物販収入など)と比較して最も大きな割合を占めているという事実は,Jクラブとスポンサーシップ契約を締結する企業との関係構築が,各クラブの収益向上や持続的な成長を目指すうえで極めて重要な視点になり得ることを物語っています.
しかしながら,現実には,時間の経過や市場環境の変化などの影響によって,クラブとスポンサー企業との関係が強化されたり,あるいは解消されたりする可能性が存在しているにも関わらず,クラブとスポンサー企業間のパートナーシップが,どのようにして強化または解消されていくのかといった一連のダイナミックな過程にアプローチを行った研究は皆無の状況にありました.加えて,Jリーグにおけるスポーツスポンサーシップの現状について,特にJ2リーグとJ3リーグに所属するJクラブでは,小口のスポンサーが多いことから,高額かつ安定したスポンサー収入の獲得が難しいといった指摘がなされてきました.このような市場環境のなかで,J2クラブやJ3クラブにみられるような比較的経営規模の小さなプロスポーツクラブは,企業とのスポンサーシップ契約の締結に向けて,どのような視点のもと,どのようなタイミングで,どのような交渉を行っていかなければならないのでしょうか.
こうした学術的・実践的な背景を踏まえ,本研究では,サッカーJ2リーグに所属する水戸ホーリーホックとそのオフィシャルパートナー企業であるJX金属株式会社(以下「JX金属」とします)のパートナーシップ形成・強化過程に関するケーススタディを通じて,プロスポーツクラブと企業のパートナーシップが形成・強化される要因を明らかにすることを目的としました.
研究対象の選定と調査・分析の方法
本研究の対象となった水戸ホーリーホックでは,1994年のクラブ創立当初から親会社を持たない,いわゆる「市民クラブ」としての経営体制が維持されてきました.2000年のJリーグ参入以降,クラブの経営は多くの困難に直面してきましたが,2011年以降の営業収益は緩やかな増加傾向をみせており,2022年度には10億円超の営業収益(前年度比約123%),および5億円を超えるスポンサー収入(前年度比約162%)を記録するに至っています(図1).さらに,地域活動という文脈においても,Jリーグ全体でもトップクラスの活動回数を誇ってきたという経緯を有するだけではなく,地域課題と連動した農事業「GRASS ROOTS FARM」の立ち上げ,ホームタウン各市町村による所属選手(ホームタウンPR大使)のドラフト会議など(いずれも関連する取り組みが「Jリーグシャレン!アウォーズ」を受賞)といったように,他のJクラブでは確認されないような独自の地域活動が新しく実行されるといった光景も生まれていました.
Jクラブ経営におけるビジネス化戦略(マネジリアル・マーケティング)とローカル化戦略(ソーシャル・マーケティング)という2つのマーケティング戦略をめぐっては,これらの戦略が必ずしも相乗効果を生み出す関係となるわけではなく,時としてトレードオフまたは二律背反の関係になり得ることが指摘されてきました(山本悦史・中西純司,Jクラブ経営におけるビジネス化戦略とローカル化戦略の諸相 : ABCDモデルを用いたマーケティング・ジレンマの発生可能性の推察,スポーツ産業学研究第32巻第1号,pp.97-116,2022年).したがって,これらの2つのマーケティング戦略を両輪とした経営を展開する水戸ホーリーホックの実践は,プロスポーツクラブ経営という理論カテゴリーにおいて次世代の代表モデルになる可能性をもつ「先端事例」と位置づけることができます.
このとき,水戸ホーリーホックの成長に大きな影響を及ぼしたと考えられるスポンサー企業(JX金属)とのパートナーシップ形成・強化過程を多様な角度から分析・解釈するといった作業は,地域活動と連動させたスポーツスポンサーシップの展開,さらにはこれらを可能にするためのイノベーション戦略に関わる科学的知見の蓄積という点においても一定の意義を有していると言えます.そこで,ここでは,JX金属と水戸ホーリーホックの間ではじめてオフィシャルパートナー(プラチナパートナー)契約が締結されてから,その後,最上位カテゴリーであるトップパートナー契約への変更が発表されるまでの期間(その前後の期間を含む)において,JX金属側で展開された意思決定および合意形成のプロセスを追跡することを試みることにしました.具体的には,ドキュメント資料の収集,関係当事者に対するインタビュー調査,さらには約16ヶ月間の参与観察といった複数の調査手法を採用し,両組織間のパートナーシップ形成・強化要因に関する質的分析を実行しました.
結果および考察
調査・分析の結果,JX金属と水戸ホーリーホックのパートナーシップ形成・強化の過程では,①パートナー企業における資源動員の創造的正当化,②クラブに対する共感の醸成,といった2つの要因が重要な役割を果たしていた可能性が示唆されました(図2).また,JX金属内部における資源動員の正当化プロセスにおいては,多様な理由(正当性)の共存状態,オピニオンリーダーの存在,組織特性(構造・文化・規模)といった3つの事象が確認されました.それと同時に,水戸ホーリーホックに対するJX金属の共感が醸成されていく過程では,クラブのビジョン・ミッション・ブランドプロミス,経営改革,ブランドイメージといった3つの要素に対する共感が生まれていたことが明らかになりました.
本研究の結果からは,複数の実践的インプリケーションを導き出すことができると考えています.特に注目すべき点として,新規パートナーの開拓や既存のパートナー企業との関係強化を目指すプロスポーツクラブの経営においては,ターゲットとなる企業の組織内部における「資源動員の正当化プロセス」の実態を適切に把握・理解し,これらの正当化を促進するための「理由(正当性)」を効果的に生み出していくことが重要であると考えられます.当初,広告宣伝に関わる取り組みとしてスタートしたJX金属と水戸ホーリーホックのパートナーシップについても,両組織間の緊密なコミュニケーションを通じて,JX金属の社内では,次第に全国各地に点在する各事業所間の一体感やコミットメントの醸成,さらにはESG経営の推進などといった多様な理由が創造され,これらがJX金属の社内ステークホルダーに共有されていく様子が確認されました.
加えて,パートナー企業からの「共感」を引き出していく過程では,クラブの存在意義を前提としながら,目指すべき未来像からバックキャストするといった「物語り戦略(Narrative Strategy)」を展開していくことが重要です.JX金属と水戸ホーリーホックの契約締結が,不確実性が高く,客観的な経済成果を見出すことが難しい段階において可能になった際にも,水戸ホーリーホックによるビジョン・ミッション・ブランドプロミスを前面に押し出した「物語り戦略」が展開されていました.また,ここでは,労務管理や人事制度,組織の心理的安全性などに関わる経営改革を遂行し,クラブにおける組織能力の向上を図りながら,パートナー企業に対して大小様々な成功体験を提供しつづけていくことが,パートナー企業との関係強化という点において一定の有効性を発揮する可能性もあわせて示唆されました.さらには,クラブ独自のブランドイメージを構築するための具体的な実践を継続していくこと,あるいは,既に構築されたブランドイメージと適合性が高い企業をターゲットとしたスポンサーセールスを展開していくことも,パートナー企業の新規獲得や関係強化の促進要因になり得るということが明らかになりました.
そして,プロスポーツクラブとのパートナーシップ契約をすでに締結している企業,あるいは今後,プロスポーツクラブとの間における契約締結を実行・検討しようとしている企業においても,クラブやこれらを取り巻く多様なステークホルダー(地方自治体や他のオフィシャルパートナー企業,サポーターなど)との間で「共通価値の創造(Creating Shared Value)」を図り,これらの実現に向けた取り組みを主体的かつ積極的に展開していくことによって,これまでには得られなかったような経営成果(認知度や従業員満足の向上,地域社会における信頼の獲得や新たなネットワークの構築など)が生み出される可能性が示されました.
まとめにかえて
最後に,本論文のDOI(Digital Object Identifier)は,水戸ホーリーホックの公式ホームページや公式SNSなどでも広く公開され,各方面から大きな反響をいただきました.また,クラブのスポンサー営業等の場面においても,スポンサーシップアクティベーションの参考事例として本論文をご紹介いただき,新規スポンサーの獲得や既存のスポンサーとの関係構築・強化の一助としていただきました.この場をお借りして,本研究にご協力くださったJX金属の川口義之氏,さらには水戸ホーリーホック代表取締役社長の小島耕氏と執行役員の瀬田元吾氏をはじめとするクラブ関係者の皆様,水戸ホーリーホックを愛するサポーターの皆様,そして本論文をご覧になってくださったすべての皆様に心より御礼を申し上げます.この度は誠に有り難うございました.



-2-1024x576.png)
-2-1024x576.png)