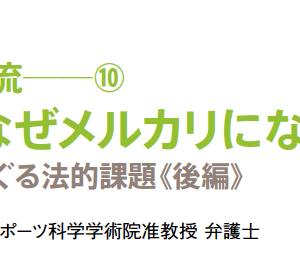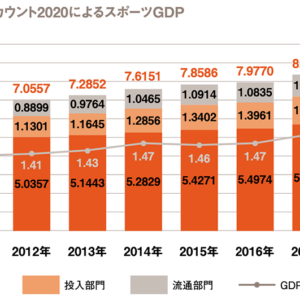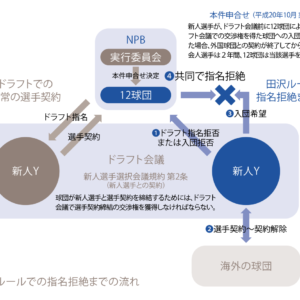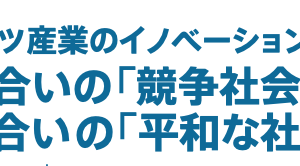第1回 ラグビー・アイルランド代表チームの謎
連載 スポーツと国家
第1回 ラグビー・アイルランド代表チームの謎
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 木村俊太
オリンピック、ワールドカップ、世界選手権……スポーツではしばしば各国代表の戦いが行われるが、そもそも国(国家)とは何なのだろうか。多くの人は自明だと思われるかもしれない。しかし、国単位での出場が原則であるはずのオリンピック代表チームに台湾や香港などが含まれることを想起するだけで、それがけっして自明ではないことがわかる。スポーツにおける国代表を見ることで、私たちが当たり前だと思っていた「国家観」は大きく揺らぐ。そんな揺らぎを連載形式で見ていきたい。第1回目の本稿ではラグビー・アイルランド代表チームを取り上げる。
はじめに
私たち日本人が「イギリス」と呼んでいる国の正式名称は「United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)」。「UK(連合王国)」と略されることも多い。別々だった4つの国(Country)が同君連合という形で一つの主権国家を形成している。その4つとは、グレートブリテン島にある、イングランド、スコットランド、ウェールズと、アイルランド島の北東部にある北アイルランドである。アイルランド島の大半はアイルランド共和国(アイルランド)という、イギリスとは別の主権国家だ。
長年にわたり、アイルランドはイギリス(あるいはイングランド)の事実上の植民地だった。アイルランド独立後も、アイルランドと北アイルランドとの間に国境線が引かれてしまったことで、その両国の争いの最前線は、南北アイルランドに持ち込まれることになる1。アイルランド島という一つの島が南北に分断され、互いにいがみ合い、時に武力衝突まで起こるという不幸な歴史を紡ぐことになってしまった。
ところが、スポーツ界においてはそんな衝突が続いてきたとは思えぬ事例が存在する。それが今回取り上げる「ラグビー・アイルランド代表チーム」である。実は、ラグビー・アイルランド代表チームはアイルランド共和国の代表チームではなく、アイルランド共和国と北アイルランドの合同チーム(地理的に言えばアイルランド島全体の代表チーム)なのである。テストマッチと呼ばれる国代表どうしの対戦はもちろん、欧州6か国対抗戦のシックスネイションズ、ラグビー・ワールドカップ、そして7人制のオリンピックにもこの国を跨いだ合同チームで出場している。国家単位での出場を基本とするオリンピックでIOCがこの合同チームを認めているのは謎である。南北アイルランドの紛争がなんとかおさまっている中、わざわざ分断を煽るのはよくないと判断したのかもしれない。
スポーツの国際大会に出場する代表チームが、なぜ国境を跨いだ合同チームなのだろうか。なぜ、そのようなチームが作られ、現在までも続いているのだろうか。
イングランドによるアイルランド支配
12世紀後半、イングランドによるアイルランドへの侵攻が始まった。ローマ教皇がアイルランドの教会を統制下に置こうとして、イングランド王ヘンリ2世にアイルランドの支配権を与えたことがきっかけだった。
こうして、アイルランドでは主にローマ・カトリック教会の信者が増えていったが、ここに大きな影響を与えたのが、16世紀半ばのイングランドでの宗教改革だ。国王主導で一気にプロテスタント化していったイングランドの影響力は、当然、アイルランドにも及ぶことになった。アイルランドの支配層(地主層)としてやってきたイングランド出身のプロテスタントたちは、圧倒的多数のカトリック信者たちに対して、植民地的な社会構造を作り上げていった2。
1845年、アイルランドで「ジャガイモ飢饉」と呼ばれる大飢饉が起こった。当時のアイルランドは肥沃な農業地帯であり、イギリス本国の食糧生産拠点だったが、イギリス本国はアイルランドの住民よりも本国の人たちを優先した。アイルランドで採れた少ないジャガイモや小麦などの生産物の多くが、イギリス本国へと輸送された。アイルランドではこの5〜6年だけで150万人以上の餓死者を出した3。
これを契機にアイルランドの人々(カトリックの被支配層)は、イギリス本国及び本国出身のアイルランドの地主の人々(プロテスタントの人々)に対する強い不満を募らせた。深まった亀裂はその後も解消されず、1998年まで続いた北アイルランド紛争など、現代にまで影響を及ぼすこととなった4。
ラグビー・アイルランド代表はどのように誕生したのか
こうした歴史的背景から、アイルランド共和国は被支配層のカトリック信者が多く、北アイルランドは支配層のプロテスタント信者が多い。そんな長年いがみ合ってきた者どうしが、ラグビー・アイルランド代表として同じチームメイトとなって国際大会を戦う。ラグビーにおける「ノーサイドの精神」といった文脈で語られることも少なくないが、それは後付けの話で、現実は少し異なる。
ラグビーをアイルランドに持ち込んだのは、イギリス本国出身の地主たちだった。プロテスタントの地主たちは、その多くが北アイルランドに居住し、ラグビーもまずは北アイルランドから広まった。その後、富裕な地主たちはアイルランド各地の地主となっていく。それに伴い、ラグビーもアイルランド各地に広まっていった。1879年にはアイルランド島全体のラグビーを統括する団体として、アイルランドラグビー協会(IRFU)が設立された。
ところが、1920年にアイルランドがイギリス本国から自治権を得ると、アイルランド国内で内乱が勃発する。連合王国(イギリス)に残りたい北部の地主層(富裕層プロテスタント)と、独立したい南部の労働者層(一般層・貧困層カトリック)との戦いが勃発する。結局、1922年、南部はアイルランド自由国(のちのアイルランド共和国)となる一方、北部は北アイルランドとして連合王国に留まり、北部と南部との間に現在まで残る国境線が引かれることとなった。この時の内乱は非常に激しく、南北アイルランド間に禍根を残すこととなった。
しかし、ラグビー・アイルランド代表はこの内乱を経ても分断されることはなかった。これには主に2つの理由があったという。1つは「ラグビーは南北両方の私立学校でプレーされていたし、ブルジョア階級の多くにとって学生時代の古い絆は地図上の新しい境界線よりも重要だった」から。もう1つは「統一チームを維持するためには、多くの人々が苦渋の選択を余儀なくされたが、北が競技の競争力を保つためにはそれしかなかった」5からだ。この時期にはすでに、プロテスタントの支配層(地主層)はアイルランド島各地(南北両地域)に広く居住していたが、彼らは学生時代から一緒にラグビーをしてきた仲間であり、彼らの間に国境線が引かれても、その絆が切れることはなかった。さらに、もし南北が分断され、南北が別々のチームになってしまったら、特に北アイルランドの競技力の低下は必至であるため、それは避けたいという事情もあったということだ。
こうして、ラグビー・アイルランド代表チームは、南北アイルランドの間に国境線が引かれたあとも、一つのチーム(IRFUという一つの団体)として存続し、現在に至っている。
国境を溶かす“Ireland’s Call”
先ほど、ラグビーにおけるノーサイドの精神といった文脈で語られるのは後付けの話だと書いた。ただ、後付けとはいえ、南北の「ノーサイド」に少なからず貢献しているのもまた事実である。
北アイルランド紛争が続いていた時代でも、代表チームに北アイルランドの治安部隊の隊員(プロテスタント)が選ばれたことがあった。彼らは、カトリックの武装集団・アイルランド共和軍(IRA)との戦いのさなかにあった。それでも、アイルランド代表のジャージに身を包んだら、互いのすべての違いは脇に置くのだと語っている5。
1998年、ようやくイギリスとアイルランドの間で、北アイルランド紛争に関する和平合意(ベルファスト合意)が結ばれた。アイルランド共和国や北アイルランドの人たちの中には、両国の平和のために、何よりもこのベルファスト合意を最優先すべきだと考えている人も少なくない。ラグビー・アイルランド代表チームをベルファスト合意の象徴だと捉える人もいるという6。
ラグビー・アイルランド代表チームが試合前に歌うのは国歌ではない。アイルランド共和国と北アイルランドの合同チーム用に作られた「Ireland’s Call」という歌である。そこではこう歌われる。
Ireland, Ireland, together standing tall! Shoulder to shoulder, we’ll answer Ireland’s call!
(アイルランド、アイルランド、一緒に立ち上がろう! 肩を組んで、アイルランドの呼び声に応えよう!)
肩を組み、この歌を歌うアイルランド島の人たちにとって、国家とはいったい何なのだろうか。少なくともこの歌を歌い、ラグビーの試合が行われている間はアイルランド島に引かれた国境線は溶けてなくなっている。
参考文献 (1)北野充2022『アイルランド現代史 独立と紛争、そしてリベラルな富裕国へ』(中央公論新社) (2)榎本雅之2016「世紀転換期のアイルランドにおけるエリート層のスポーツライフ アイルランドラグビーの父 C.B.バリントン(1848-1943)に着目して」『彦根論叢 2016 summer/ No.408』(滋賀大学経済経営研究所) (3)徳永哲(2005)「アイルランド、ジャガイモ大飢饉研究」『日本赤十字九州国際看護大学intramural research report』(日本赤十字九州国際看護大学) (4)波多野裕造(1994)『物語 アイルランドの歴史 欧州連合に賭ける“妖精の国”』(中央公論新社) (5)ウィリアム・アンダーヒル2019「ラグビーが統合する南北アイルランド」ニューズウィーク日本版 2019年9月26日付(https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/09/post-13050_1.php)(2025年4月21日閲覧) (6)木村正人2019「【ラグビーW杯】アイルランド代表はどうして2つの旗を掲げ、自分たちの国歌を歌わないのか」YAHOO! JAPANニュース エキスパート 2019年10月13日付(https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/4116f7e3947ea7fb37e02bd907ab22c03b2dd985)(2025年4月21日閲覧)