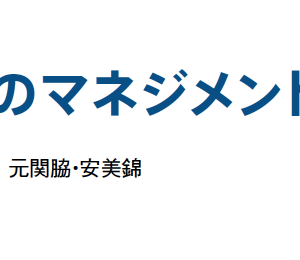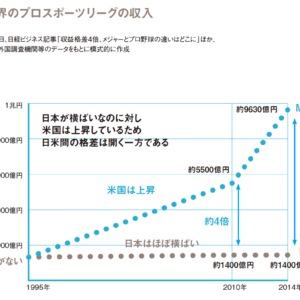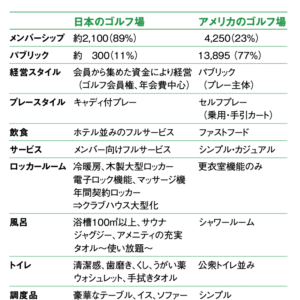【2】スポーツ文化とスポーツ産業の構図
【2】スポーツ文化とスポーツ産業の構図
元愛知大学教授 新井野洋一
スポーツと文化について
《本書》では、「スポーツとは何か」について、「一義的に定めることは難しく、ある人がスポーツとみなすものはスポーツである」という、身近な目前の現代(の)スポーツに視点を当て議論が進められています。換言すれば、《本書》におけるスポーツとは産業革命以降のスポーツと言えます。企業すなわち諸資源を使って事業を行い社会が必要とする商品やサービスを提供する利益追求の組織の出現がスポーツ産業の発展を促したと考えられるからです。したがって、スポーツ産業とは、「企業によってスポーツに関連するモノやコトが生産される事業」と再定義できるでしょう。
一方、スポーツ文化は、”文化としてのスポーツ”を短縮した表現です。2000年のスポーツ振興基本計画において、スポーツを世界共通の人類の「文化である」と定義して以来、スポーツ文化という言葉はさまざまな分野で援用されてきました。しかし、そこでは、スポーツが文化であることは自明のこととされ、その実相について十分に説明されていないように思われます。
スポーツが文化であるとは
スポーツ産業を”スポーツ文化”を産み出す経済活動と《本書》では定義していますが、その真意を補足するため、”スポーツ文化”の成立要件について復習してみましょう。
第一は、私たちがスポーツをする、みる、ささえる、つくる際には、スポーツに対する思いや考え方、つまりスポーツ観念が内在しています。その一方が健康を維持・向上させる、名誉を得る、経済を活発にさせる、まちをにぎやかにするといった諸課題を実現する手段としてスポーツを活用しようとする考え方です。もうひとつは、スポーツを自由に楽しむ経験そのものに目的があるとする考え方です。風を受けながらのランニングや、めまいを感じるようなスケボーの滑走などの瞬間にこそ意味があるとする考え方です。
第二に、スポーツには、工夫された合理的な行動様式があるということです。その一つが、ルールや競技規則のような遵守されなければならない法的規範(罰則がある)とフェアプレーやスポーツマンシップなどの道徳的規範(実行されることが望ましい行動基準)に大別されるスポーツ規範です。もう一つのスポーツ行動様式はスポーツ実践を支える技術や戦術、戦略などに関する合理的な仕方や方法です。
第三は、スポーツ物的事物です。私たちがスポーツ文化を視覚的に認識できるのは、施設や設備、用具、用品が存在するからです。リングがなければボクシングはできない、弓と矢がなければ弓道はできない、水着がなければ水泳はできないのです。そして、それらは安全性と合理性、機能性、公平性を条件に開発、生産、販売されてきました。
スポーツ興行の現場は、これら3要件が複雑に絡み合っています。人々は、「この時、この場所、この感動を共有したい」というスポーツ観念に誘発され、チケットを購入し、スポーツ興行に足を運び、応援団に合わせてエールを送り、合間を見て食事を摂り、土産のグッズを買う観客の役割を獲得しているのです。
以上のように、現代スポーツは、観念的・行動的・物質的な成果を見事に表出させており、紛れもなく文化と言えます。したがって、スポーツ産業とは、スポーツ文化を深く理解し、賢く活用するビジネスと表現することもできるでしょう。
スポーツ産業の世界
スポーツ産業を図式的に考えると、「ゴルフをしたい」「プロバスケットの試合を観たい」「少年野球のコーチをしたい」という消費者と「スポーツをする施設・道具をつくりたい」「観戦の方法と手段を提供したい」「指導者育成に支援したい」という生産者とのスポーツ文化をめぐる需要-供給関係が核となっています。
しかし、それだけでスポーツ産業は成立できません。スポーツ文化の安定的な発展を図る法・制度や政策を提案、決定する立法府や、スポーツ施設の整備や運営の拡充などに向けた公共サービスを担う行政も重要なセクターです。さらには、メディアや金融機関、教育機関、市民団体などの地域セクターは、スポーツ活動の実現と発展にとって大きな意味を持っています。加えて、スポーツ組織やスポーツ団体の存在は重要な役目を持っています。スポーツ産業の世界は、数多くのステークホルダーの連携と協働によって成立しているのです(図を参照)。
スポーツ文化の変容とスポーツ産業の拡がり
スポーツ文化は、スポーツ以外の一般的な文化の存在を前提として発展してきましたが、その逆の様相も見られるようになってきました。例えば、1/100秒を争うスポーツ種目において力の差が縮まったことから精度の高い計測機器が開発、使用されるようになり、その機能が日常使用する腕時計にまで波及しています。スポーツウェアが日常のファッションウェアとして流行したり、スポーツ施設建設で用いられた新たな建築技術が一般の建築物に応用されたりという例も顕著になっています。
このように、スポーツ文化を産み出す経済活動であるスポーツ産業は、着々と拡がりを示しています。しかし、文化は社会で伝播されることによって文化となるものです。発明しただけの状態では文化という言葉は適用されないということです。この観点に立てば、スポーツ産業は、スポーツ文化を”産み出す”にとどまらず、社会に伝播していく仕事を担っていると言えましょう。
スポーツ文化は、旧来から、生活必需財として扱われてきませんでした。会社や学校が経営困難になるとスポーツクラブの廃部やスポーツ事業への支援の打ち切りといった、リストラの第一候補とされてきました。大災害や大事故の発生時には、スポーツ施設が避難所や遺体安置所、仮設住宅地として利用され、スポーツ実践の場を奪われてきました。そんな中で、避難場所となったスポーツ施設が不便で不健康な場所であったいう批判と教訓から、スポーツ施設の補修やアリーナ・スタジアム建設計画を見直す政策が動きつつあります。また災害時でも健康維持のために身体活動が必要であることが国民の共通理解になりつつあります。加えて、著名なアスリートが避難所を訪問し被害者に笑顔をとり戻す機会をつくったことや、スポーツ団体がボランティア派遣や義援金運動に大きな役割を示したことを私たちは知っています。以上は、喜ばしい明るい話題です。
問題は、これらの行為や活動がスポーツ産業を基盤に発揮されることを社会に説明してこなかったことだと思われます。スポーツ産業学の研究テーマとして議論されることが期待されます。(続)
【参考文献】佐伯聰夫「スポーツの文化」菅原禮編著『スポーツ社会学の基礎理論』不昧堂出版,67-98(1984)/中西純司「文化としてのスポーツの価値」『人間福祉学研究』第5巻第1号、(2012)/新井野洋一「大学におけるスポーツ文化教育の再考」『愛知大学体育学論叢』31号、(2024)